働く原動力の”目指すもの”を実現させましょう!より良い経営環境・職場づくりを提案します。 大阪市 八尾市の 社会保険労務士法人 大竹事務所
【大阪事務所】
〒541-0046 大阪市中央区平野町2-5-14 FUKU BLD.三休橋301 (地図)
〒541-0046 大阪市中央区平野町2-5-14 FUKU BLD.三休橋301 (地図)
- トップページ
- >
- News
【東京の士業交流会に参加してきました】
カテゴリ : Staff Blog
2025-11-18 15:23:38
「渋沢栄一に学ぶ “信頼される経営者”の条件とは?」
カテゴリ : Staff Blog
「社員がついてこない」「信用されていない気がする」──
こんな悩みを、誰にも言えず抱えていませんか?
そんな今こそ、明治の実業家・渋沢栄一に学ぶ価値があります。
渋沢は、第一国立銀行や王子製紙、東京証券取引所など約500の企業に関わり、日本の資本主義の礎を築いた人物。
でも単なる“金儲け”の人ではありません。彼が大切にしたのは「論語と算盤(そろばん)」──つまり“道徳”と“利益”の両立です。
「商売は、人を欺いてはならぬ」
「社員を家族のように思え」
そんな言葉を残し、どんな事業でも“人を大切にすること”を経営の軸としました。
富岡製糸場の民営化にも深く関わった渋沢は、女工たちの教育環境や待遇の整備にも力を注ぎました。
利益を追うだけでなく、「人材を育てる場」としての工場づくりに本気だったのです。
現代でも「会社は人なり」とよく言います。
でも現実には、人を“コスト”と見る企業も少なくありません。給与や制度を整えるのは当然として、「この会社にいて良かった」と社員が思えるかどうか。
それは制度だけではなく、『経営者の“あり方”』にかかっています。
渋沢栄一が生きた時代とは、もちろん背景が違います。けれど、信頼される経営者の本質は、今も変わりません。
社労士として多くの中小企業を見てきましたが、信頼される経営者に共通するのは、「何を言うか」より「どう生きているか」がブレていないこと。
皆さまの会社では、何が“信頼の土台”になっていますか?
渋沢栄一の生き方をヒントに、今一度、立ち止まってみるのも悪くありません。
おおたけ
こんな悩みを、誰にも言えず抱えていませんか?
そんな今こそ、明治の実業家・渋沢栄一に学ぶ価値があります。
渋沢は、第一国立銀行や王子製紙、東京証券取引所など約500の企業に関わり、日本の資本主義の礎を築いた人物。
でも単なる“金儲け”の人ではありません。彼が大切にしたのは「論語と算盤(そろばん)」──つまり“道徳”と“利益”の両立です。
「商売は、人を欺いてはならぬ」
「社員を家族のように思え」
そんな言葉を残し、どんな事業でも“人を大切にすること”を経営の軸としました。
富岡製糸場の民営化にも深く関わった渋沢は、女工たちの教育環境や待遇の整備にも力を注ぎました。
利益を追うだけでなく、「人材を育てる場」としての工場づくりに本気だったのです。
現代でも「会社は人なり」とよく言います。
でも現実には、人を“コスト”と見る企業も少なくありません。給与や制度を整えるのは当然として、「この会社にいて良かった」と社員が思えるかどうか。
それは制度だけではなく、『経営者の“あり方”』にかかっています。
渋沢栄一が生きた時代とは、もちろん背景が違います。けれど、信頼される経営者の本質は、今も変わりません。
- 嘘をつかない
- 社員の人生を思いやる
- 経済と倫理のバランスをとる
社労士として多くの中小企業を見てきましたが、信頼される経営者に共通するのは、「何を言うか」より「どう生きているか」がブレていないこと。
皆さまの会社では、何が“信頼の土台”になっていますか?
渋沢栄一の生き方をヒントに、今一度、立ち止まってみるのも悪くありません。
おおたけ
2025-11-01 09:00:00
2025.11.1「事務所通信11月号をUPしました!」
「渋沢栄一に学ぶ “信頼される経営者”の条件とは?」
カテゴリ : Staff Blog
「社員がついてこない」「信用されていない気がする」──
こんな悩みを、誰にも言えず抱えていませんか?
そんな今こそ、明治の実業家・渋沢栄一に学ぶ価値があります。
渋沢は、第一国立銀行や王子製紙、東京証券取引所など約500の企業に関わり、日本の資本主義の礎を築いた人物。
でも単なる“金儲け”の人ではありません。彼が大切にしたのは「論語と算盤(そろばん)」──つまり“道徳”と“利益”の両立です。
「商売は、人を欺いてはならぬ」
「社員を家族のように思え」
そんな言葉を残し、どんな事業でも“人を大切にすること”を経営の軸としました。
富岡製糸場の民営化にも深く関わった渋沢は、女工たちの教育環境や待遇の整備にも力を注ぎました。
利益を追うだけでなく、「人材を育てる場」としての工場づくりに本気だったのです。
現代でも「会社は人なり」とよく言います。
でも現実には、人を“コスト”と見る企業も少なくありません。
給与や制度を整えるのは当然として、「この会社にいて良かった」と社員が思えるかどうか。
それは制度だけではなく、『経営者の“あり方”』にかかっています。
渋沢栄一が生きた時代とは、もちろん背景が違います。けれど、信頼される経営者の本質は、今も変わりません。
社労士として多くの中小企業を見てきましたが、信頼される経営者に共通するのは、「何を言うか」より「どう生きているか」がブレていないこと。
皆さまの会社では、何が“信頼の土台”になっていますか?
渋沢栄一の生き方をヒントに、今一度、立ち止まってみるのも悪くありません。
おおたけ
こんな悩みを、誰にも言えず抱えていませんか?
そんな今こそ、明治の実業家・渋沢栄一に学ぶ価値があります。
渋沢は、第一国立銀行や王子製紙、東京証券取引所など約500の企業に関わり、日本の資本主義の礎を築いた人物。
でも単なる“金儲け”の人ではありません。彼が大切にしたのは「論語と算盤(そろばん)」──つまり“道徳”と“利益”の両立です。
「商売は、人を欺いてはならぬ」
「社員を家族のように思え」
そんな言葉を残し、どんな事業でも“人を大切にすること”を経営の軸としました。
富岡製糸場の民営化にも深く関わった渋沢は、女工たちの教育環境や待遇の整備にも力を注ぎました。
利益を追うだけでなく、「人材を育てる場」としての工場づくりに本気だったのです。
現代でも「会社は人なり」とよく言います。
でも現実には、人を“コスト”と見る企業も少なくありません。
給与や制度を整えるのは当然として、「この会社にいて良かった」と社員が思えるかどうか。
それは制度だけではなく、『経営者の“あり方”』にかかっています。
渋沢栄一が生きた時代とは、もちろん背景が違います。けれど、信頼される経営者の本質は、今も変わりません。
- 嘘をつかない
- 社員の人生を思いやる
- 経済と倫理のバランスをとる
社労士として多くの中小企業を見てきましたが、信頼される経営者に共通するのは、「何を言うか」より「どう生きているか」がブレていないこと。
皆さまの会社では、何が“信頼の土台”になっていますか?
渋沢栄一の生き方をヒントに、今一度、立ち止まってみるのも悪くありません。
おおたけ
2025-11-01 08:00:00
「歴史から学ぶ人材育成 ~富岡製糸場に見る“学びながら働く”職場づくり~」
カテゴリ : Staff Blog
「即戦力が欲しい」と嘆く経営者の声を、よく耳にします。ですが、本当に“育てる文化”は社内に根付いているでしょうか?
140年以上前、明治政府が設立した富岡製糸場には、今の企業にも通じる「人材育成」のヒントが詰まっている気がします。
富岡製糸場の目的は、生糸の大量輸出による外貨獲得だけでなく、全国に製糸技術を広める「人づくり」でもありました。
ここに集められたのは、各地から集まった若い女性たち。
当時としては破格の待遇――労働時間は1日7時間45分、日曜休み、医療費や食費は国の負担。
さらに、裁縫や読書、習字などの“学びの場”が、職場内に整えられていました。
初代所長・尾高惇忠は、技術だけでなく「誇り」を育てようとした人物です。
実際に、ここで学んだ女工たちは郷里に戻って指導者となり、製糸業を全国へと広めていきました。
単なる“労働力”ではなく、“技術と志を持った人材”を育てていたのです。
これはまさに、「働きながら学ぶ」=“ワークプレイス・ラーニング”の先駆けと言えるでしょう。
一方で、現代の職場では「忙しくて教える余裕がない」「OJT=放置」なんてことも…。
でも、成長する場を用意しなければ、人は定着せず、組織は疲弊していきます。
富岡製糸場が示したのは、「職場は、学びの場にもなりうる」という考え方。
そして“教える側”が本気で育てる姿勢を見せたとき、若手は驚くほど力を発揮するという事実です。
制度や研修も大切ですが、まず問いたいのは“職場の育成観”。
皆さまの会社では、働く人が「ここで学べる」「成長できる」と感じているでしょうか?
おおたけ
140年以上前、明治政府が設立した富岡製糸場には、今の企業にも通じる「人材育成」のヒントが詰まっている気がします。
富岡製糸場の目的は、生糸の大量輸出による外貨獲得だけでなく、全国に製糸技術を広める「人づくり」でもありました。
ここに集められたのは、各地から集まった若い女性たち。
当時としては破格の待遇――労働時間は1日7時間45分、日曜休み、医療費や食費は国の負担。
さらに、裁縫や読書、習字などの“学びの場”が、職場内に整えられていました。
初代所長・尾高惇忠は、技術だけでなく「誇り」を育てようとした人物です。
実際に、ここで学んだ女工たちは郷里に戻って指導者となり、製糸業を全国へと広めていきました。
単なる“労働力”ではなく、“技術と志を持った人材”を育てていたのです。
これはまさに、「働きながら学ぶ」=“ワークプレイス・ラーニング”の先駆けと言えるでしょう。
一方で、現代の職場では「忙しくて教える余裕がない」「OJT=放置」なんてことも…。
でも、成長する場を用意しなければ、人は定着せず、組織は疲弊していきます。
富岡製糸場が示したのは、「職場は、学びの場にもなりうる」という考え方。
そして“教える側”が本気で育てる姿勢を見せたとき、若手は驚くほど力を発揮するという事実です。
制度や研修も大切ですが、まず問いたいのは“職場の育成観”。
皆さまの会社では、働く人が「ここで学べる」「成長できる」と感じているでしょうか?
おおたけ
2025-10-27 18:00:00
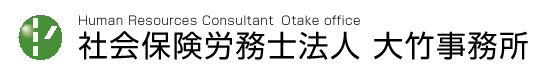




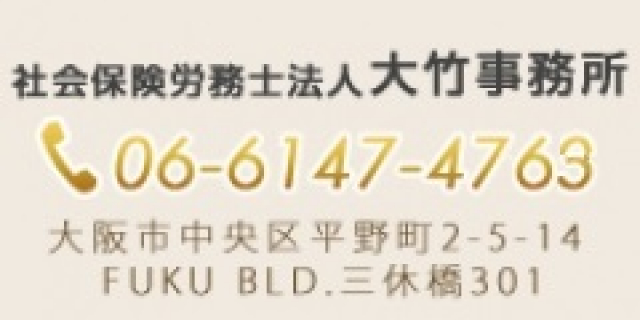


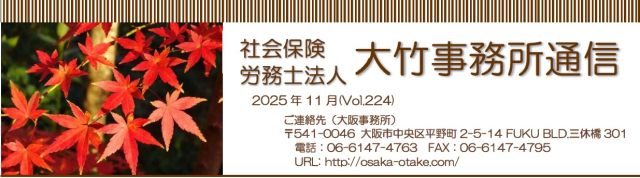





総勢100名ほどの先生方が一堂に会し、その熱量に思わず圧倒されてしまいました。
この仕事を始め色んな方々と出会う機会が増えたものの、これほどの規模になると簡単には話しかけに行けないものですね^^;
とはいえ時間も費用もかけて参加している以上、「何かひとつは持ち帰ろう」という思いで、そーっと足跡を残しながら、控えめに営業活動(?)もしてまいりました。
また今回特に印象的だったのは、幹事を務められていた社労士さんの姿勢です。
参加者への気配りや終了後に送って下さったメールの内容まで、とにかく頭が常にフル回転していることが伝わってきました。
あのスピード感と視野の広さは、本当に刺激になります。
こうした場に身を置くと、「自分も負けられないなぁ」と気持ちが新たになります。
日々の業務に加えて、学びや人とのつながりをどう活かしていくかが、これからの士業としての価値を高めていくのかもしれません。
今後も更に皆さまのお役に立てるよう、引き続き研鑽を積んでまいります。
おぎの