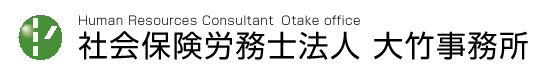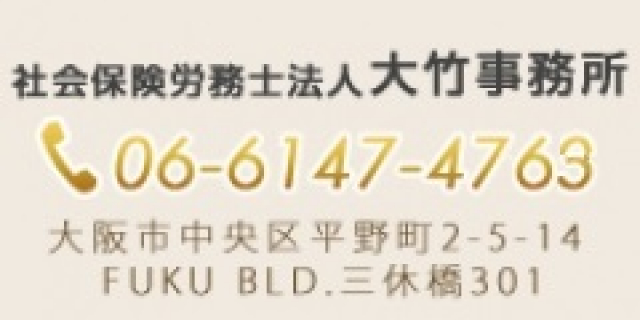「女工哀史」や『あゝ野麦峠』の影響もあり、製糸工場と聞くと「過酷な労働環境」を連想する方は多いかもしれません。
ですが、明治5年に開設された官営の富岡製糸場は、実はまったく異なる性格を持っていました。
富岡製糸場は、当時の日本における“近代化の旗艦”として、政府主導で設立された模範工場。
労働時間は1日7時間45分、日曜休み、医療費・食費は国が負担。
宿舎も完備され、読み書き・裁縫といった教養も学べる教育的な場でもありました。
「異人が乙女の生き血を吸う」といったデマが広がったとき、初代所長の尾高惇忠は、自らの13歳の娘を女工として入所させ、風評を払拭しました。
働くことへの誇りと学びの機会があり、彼女たちは技術を身につけて郷里に戻り、各地の製糸場でリーダーとなっていったのです。
一方、『あゝ野麦峠』が描くのは、時代が下った大正~昭和初期の民間製糸工場。
急速な経済成長の中で労働力の需要が高まり、過酷な長時間労働や低賃金が問題となりました。
つまり、同じ「女工」といっても、富岡製糸場とその後の民間工場では、背景も環境も大きく異なるのです。
ここには、現代にも通じる教訓があります。
働き方改革、そして「休み方改革」が叫ばれる現代。
単に労働時間を短くすれば良いのではなく、「働く場に誇りが持てるか」「成長の機会があるか」「安心して休める仕組みがあるか」といった、職場の“質”が問われているのではないでしょうか。
140年前の富岡製糸場が、実はそうした観点で設計されていたことに驚かされます。
企業として“模範”であろうとしたその姿勢こそ、いま私たちが見直すべき価値なのかもしれません。
おおたけ
働く原動力の”目指すもの”を実現させましょう!より良い経営環境・職場づくりを提案します。 大阪市 八尾市の 社会保険労務士法人 大竹事務所
【大阪事務所】
〒541-0046 大阪市中央区平野町2-5-14 FUKU BLD.三休橋301 (地図)
〒541-0046 大阪市中央区平野町2-5-14 FUKU BLD.三休橋301 (地図)
- トップページ
- >
- News
「富岡製糸場は“ブラック企業”だったのか? いま見直される近代化の原点」
カテゴリ : Staff Blog
2025-10-27 17:08:00
【結局のところ「人」が頼り?】
カテゴリ : Staff Blog
連休中に台湾を訪れたのですが、到着早々やらかしました。
空港から市街地に向かうバスに乗ったところまでは良かったのですが、降りる際にスーツケースをバスの荷物置き場に置きっぱなしにしてしまったのです。
空港に引き返した方が良いと判断し、半ば諦めながら空港のバス会社の方に相談したところ、落ち着いた様子で対応してくれました。
その後荷物は終点の台北バスターミナルに置いてくれていることがわかりました。
次に来るバスにそのまま(タダです^^)乗ると、運転手さんが荷物置き場まで連れて行ってくれるとのことで、少しの間バスを貸し切らせてもらいました。
無事荷物と再会できた時には、「荷物を置き忘れたのが台湾で良かった」と安堵しました。
もう一つ心に残ったのが、お土産屋さんでの出来事です。
商品を手に取りながら「これは事務所の皆で分けて食べやすい!ところで何個入っているのか」と心の中で考えていると、店員さんが近づいて来てくれました。
「中に○個入っています」とのこと。日本人の”察する”を理解してくれているような接客でした。
昨今働き方改革やDXなど、仕事は効率化の方向へ進んでいますが、最後に頼れるのはやはり「人」ということを感じた旅でした。
おぎの
2025-10-16 16:39:46
【(今更ながら)ふるさと納税、チャレンジです】
カテゴリ : Staff Blog
皆さん、こんにちは。
人によっては「今更にもほどがある」と思われたかもしれませんが(汗)、我が家では今年から始めてみることにしました。
以前から話を聞くたびに気にはなっていたのですが、膨大な返礼品を見たり、手続きが大変そうというイメージがあったりで二の足を踏んでおりました。
今回、妻の妹さんから「めっちゃ簡単ですよ」という話を聞き、また10月1日から制度変更により駆け込みの方が増えているといったことも聞きまして、我々も駆け込んでみることにしました。
何とか寄付の申込み自体は完了したのですが、妹さんから聞いていた「めっちゃ簡単な方法」というのができないようにしてしまったようで、、、(選ぶ自治体を5つ以内にしないといけないところ、6つにしてしまいました。)、この後の流れをきちんと確認して進めていかないといけないと気を引き締めているところです。
改めて、自分たちのお仕事に置き換えた時に、自分たちは見慣れているので「この手続きは比較的あっさりしていてやりやすい。」と思っていても、慣れない方からしたら「難しい。。。」と感じられることも十分あると思いました。
法律や制度の説明をさせて頂くことが多いので、「どのように伝えたら良いか」ということへの意識を改めてご案内をして参りたいと思いました。
にしぐち
人によっては「今更にもほどがある」と思われたかもしれませんが(汗)、我が家では今年から始めてみることにしました。
以前から話を聞くたびに気にはなっていたのですが、膨大な返礼品を見たり、手続きが大変そうというイメージがあったりで二の足を踏んでおりました。
今回、妻の妹さんから「めっちゃ簡単ですよ」という話を聞き、また10月1日から制度変更により駆け込みの方が増えているといったことも聞きまして、我々も駆け込んでみることにしました。
何とか寄付の申込み自体は完了したのですが、妹さんから聞いていた「めっちゃ簡単な方法」というのができないようにしてしまったようで、、、(選ぶ自治体を5つ以内にしないといけないところ、6つにしてしまいました。)、この後の流れをきちんと確認して進めていかないといけないと気を引き締めているところです。
改めて、自分たちのお仕事に置き換えた時に、自分たちは見慣れているので「この手続きは比較的あっさりしていてやりやすい。」と思っていても、慣れない方からしたら「難しい。。。」と感じられることも十分あると思いました。
法律や制度の説明をさせて頂くことが多いので、「どのように伝えたら良いか」ということへの意識を改めてご案内をして参りたいと思いました。
にしぐち
2025-10-06 10:17:40
2025.10.1「事務所通信10月号をUPしました!」
【ようやく暑さが和らいできました】
カテゴリ : Staff Blog
皆さまこんにちは!
最近朝晩の暑さが和らいできて、家でも職場でもエアコンを使わない日が増えてきました。
良い気候になってきたということで、大阪関西万博へ行かれる方も増えているようですね。
暑さはマシになっているものの、思ったように回れない(パビリオンなどが見られない)ということにもなっているようですね。
私は7月と8月に会場に通ったのですが、暑かったとはいえある意味良かったのかなと思っております。
暑さはマシになってはきましたが、まだ日中は30度近く上がります。
4月~5月の暑くなり始めた時期も注意が必要でしたが、マシになってきたこの時期も(自覚症状が出にくいという点で)注意が必要です。
こまめな水分補給は継続しつつ、我慢し続けてしまうことのないようにしてください。
9月に入って始めたダイエットですが、今のところ継続しております。
*①~③のいずれもです。
① 間食制度の廃止、②炭水化物の削減、③継続的な運動
家の体重計が動かなくなっているので、これも解消して乗っていくようにしたいと思います。
「食欲の秋」と言われる季節になってきたので、とめどない食欲に負けないよう頑張って参ります。
にしぐち
2025-09-30 12:27:51