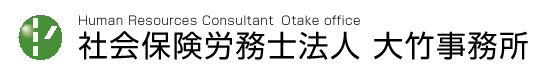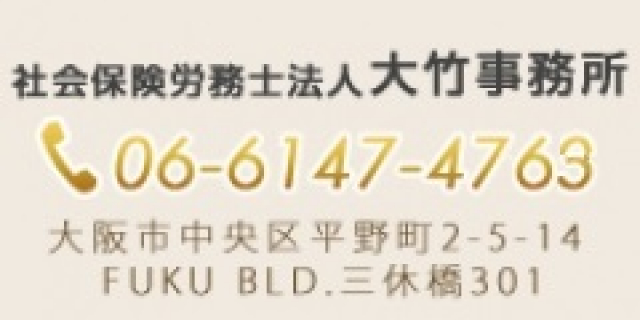採用面接、悩んでいませんか?
面接だけではなく、適性検査も重要な判断材料となります。
それを利用することで、応募者の能力や適合性をもう一つの角度から判断することができます。
適性検査はただの「テスト」ではありません。
応募者の本当の能力を引き出すためには、適切な検査を選ぶことが重要です。
適性検査を導入する際は、何を評価したいのか、その情報が採用の判断にどう役立つのかをしっかりと考えなければなりません。
先日の弊社セミナーでは、『パーソナリティ診断』のご紹介をしました。
診断結果を、採用する方だけではなく、今いらっしゃる社員さんとの比較にもご利用頂けます。
また第二弾を開催しますので、その際はご参加下さいませ。
引き続き、採用のヒントをお届けします。次回もお楽しみに^ ^
おおたけ
おおたけ